アンコンシャス・バイアス研修とは?職場での事例や目的などを解説
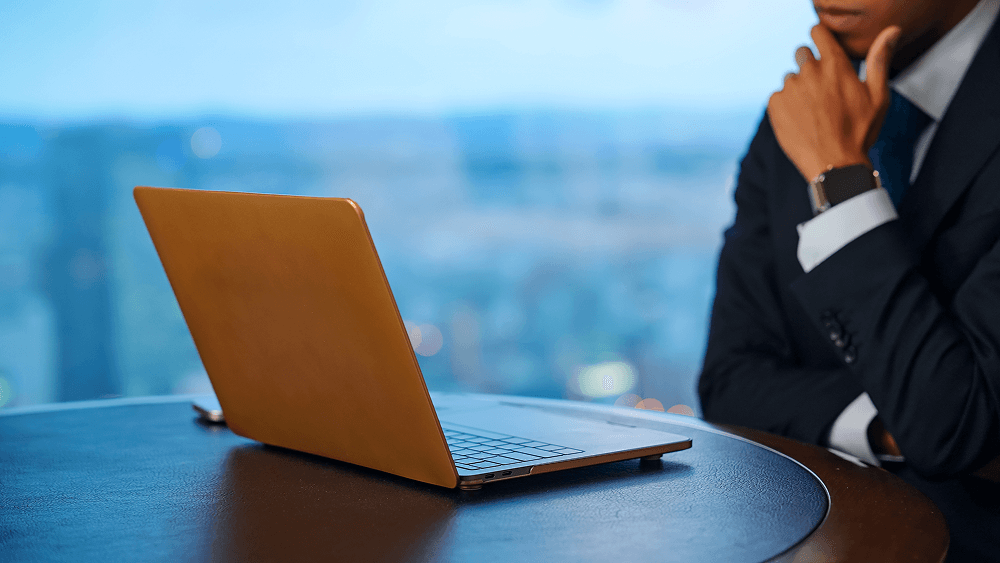
職場でのDE&Iやハラスメントやコンプライアンス対策が重要視される現代、人事担当者の皆様は「どうすれば公平で働きやすい環境を作れるのか」といった課題に直面していませんか。
その解決の鍵となるのが「アンコンシャス・バイアス研修」です。無意識の偏見を認識し、改善することで、組織全体のパフォーマンス向上と従業員満足度の向上を実現できます。
本記事では、アンコンシャス・バイアスの基本概念から職場での具体的事例、研修の目的や効果的な実施方法まで、人事担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。中小企業でも実践可能な研修プランもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
【関連記事】
アンコンシャス・バイアスの具体例20選!職場、日常などシチュエーション別にご紹介
アンコンシャス・バイアス研修とは?
まずは、用語の解説と、研修が注目される背景や、得られる効果について見ていきましょう。
アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)とは?
アンコンシャス・バイアス(Unconscious Bias)とは、「無意識の偏見」や「無意識の思い込み」と訳され、育った環境や経験、文化、教育などによって、知らず知らずのうちに特定の情報や状況に対して、偏った見方や判断をしてしまうことを指します。
たとえば、「男性はリーダーシップがある」「時短勤務の女性には重要な仕事を任せられない」「育休は女性がとるもの」といった考え方は、アンコンシャス・バイアスの一例です。
こういった無意識の偏見は、個人の行動や意思決定に影響を与え、職場においては採用、評価、配置、育成などさまざまな場面で不公平な結果を招く恐れがあります。
アンコンシャス・バイアス研修が注目される背景
アンコンシャス・バイアス研修が近年、特に注目を集めている背景には、主に以下の要因があります。
多様性(ダイバーシティ)の推進
グローバル化や少子高齢化が進む中で、企業は多様な人材(性別、国籍、年齢、障がい、LGBTQ+など)を受け入れ、その能力を最大限に引き出すことが競争力向上に不可欠です。
アンコンシャス・バイアスは多様な人材の活躍を阻害する要因となるため、その解消が求められています。
ハラスメント・差別の防止
アンコンシャス・バイアスは、時にハラスメントや差別的な言動につながることがあります。公平で安全な職場環境を構築するためには、偏見の根源を理解し、対処することが重要です。
働き方改革の進展
柔軟な働き方や個々の事情に配慮した環境づくりが求められる中で、アンコンシャス・バイアスがあると、既存の働き方や慣習を固定化させてしまい、変革を阻む恐れがあります。
アンコンシャス・バイアス研修で得られる効果
アンコンシャス・バイアス研修を導入することで、企業は以下のような効果を期待できます。
コミュニケーションの改善
相手の多様性を尊重し、決めつけや先入観に基づかない対話ができるようになり、チーム内のコミュニケーションが円滑になります。
公平な意思決定
採用、評価、人事異動などの重要な場面で、偏見に基づかない公平な判断ができるようになります。
心理的安全性の向上
従業員が安心して意見を表明し、自分らしく働ける環境を醸成できます。
組織パフォーマンスの向上
多様な視点やアイデアが活かされ、イノベーションが促進され、結果として組織全体の生産性や競争力が高まります。
Drama-style video training東映の研修動画『ドラスタ』とは?
アンコンシャス・バイアスの具体例
具体的な例を様々なケースごとにいくつか見てみましょう。
職場で見られるアンコンシャス・バイアス
職場では、さまざまな形でアンコンシャス・バイアスが見られます。人事担当者として、これらの例を認識することが、研修の必要性を理解する第一歩となります。
採用面接での具体的
- 「この大学出身者は優秀だ」「この業界経験者は即戦力になる」といった学歴や前職への過度な評価。
- 面接官と共通の趣味を持つ応募者に好印象を抱く。
- 女性応募者に対して「結婚や出産で辞めてしまうのでは」と無意識に考える。
人事評価での具体的
- 普段から目立つ成果を出している従業員を、ほかの業務でも高く評価してしまう。
- 特定の従業員の欠点ばかりに目が行き、全体的な評価が低くなる。
- 「あの人はいつも遅くまで残業しているから頑張っている」と、時間だけで評価してしまう。
チームマネジメントでの具体的
- 「若い世代はデジタルに強いはずだ」と、特定の業務を若手社員に押し付ける。
- 「男性社員は感情的にならない」と、男性の感情表現を抑制するような言動をする。
- 育児中の従業員に対して「残業はできないだろう」と、重要なプロジェクトから外してしまう。
日常生活におけるアンコンシャス・バイアス
アンコンシャス・バイアスは、職場だけでなく日常生活にも深く根付いています。
性別に関するバイアス
- 「料理は女性がするもの」「力仕事は男性がするもの」といった役割分担の固定観念。
- 「女性だから優しくて当たり前」「男性だから強くあるべき」という期待。
年齢に関するバイアス
- 「高齢者はITに疎い」「若者は社会経験が足りない」といった決めつけ。
- 「〇歳だからこうあるべき」という年齢による行動の制限。
外見に関するバイアス
- 「背が高い人は頼りになる」「眼鏡をかけている人は真面目そう」といった外見からの判断。
- 特定の服装や髪型に対する無意識の評価。
アンコンシャス・バイアス研修の目的
研修の主な目的は、以下の通りです。
多様な人材の活躍を推進する
アンコンシャス・バイアス研修は、従業員一人ひとりが持つ潜在能力を最大限に引き出し、組織全体のイノベーションを促進することを目的の一つとしています。
現代のビジネス環境において、多様な人材の確保と活用は企業の競争力に直結します。アンコンシャス・バイアス研修を行うことで、性別や年齢、国籍、価値観など、あらゆる違いを持つ人々が互いを尊重し、それぞれの能力を発揮できる包摂的な職場環境を醸成できます。
多様な背景を持つ従業員の意見が公平に評価されることで、既存の枠にとらわれない新しいアイデアや解決策が生まれやすくなります。
ハラスメントや差別をなくす
無意識の偏見は、意図せずともハラスメントや差別的な言動につながる可能性があります。研修を通じて、これらの問題の根源を理解し、予防することも、大きな目的の一つです。
アンコンシャス・バイアス研修は、無意識の偏見がどのようにハラスメントや差別につながるかを学び、自身の言動を客観的に見つめ直す機会となります。
さらに、互いの違いを認め、尊重する文化を育むことで、ハラスメントや差別が発生しにくい、心理的安全性の高い職場環境を構築します。
ハラスメントや差別は、従業員のモチベーション低下だけでなく、企業の法的リスクやブランドイメージの毀損にもつながります。研修はこれらのリスクを低減する効果も持ちます。
公平な評価や採用を実現する
人事担当者にとって最も重要な課題の一つが、公平な評価と採用プロセスの実現です。
アンコンシャス・バイアス研修は、評価や採用プロセスにおける偏見を排除し、客観的で公正な判断を促すことも目的としています。
採用プロセスにおいては、アンコンシャス・バイアス研修によって面接官が持つ無意識の偏見に気づき、応募者のスキルや経験、ポテンシャルを公平に評価できるような採用基準や面接手法の確立につながります。
また、評価者が自身の偏見に気づき、客観的な事実に基づいて評価を行うことで、評価の納得度と透明性を高められます。
さらに、従業員の能力や適性を偏見なく見極め、最適な配置や育成機会を提供することで、個々の成長と組織全体の発展を両立させられます。
アンコンシャス・バイアス研修を行うメリットは?
アンコンシャス・バイアス研修は、人事課題の解決だけでなく、企業全体の競争力強化につながる、多岐にわたるメリットをもたらしてくれます。
生産性が向上する
アンコンシャス・バイアスが解消されることで、チーム内のコミュニケーションが活性化し、業務効率が向上します。
まず、多様な意見が公平に検討され、より多角的な視点から最適な意思決定が行われるようになります。これにより、誤った判断や機会損失が減少します。
また、互いの違いを理解し尊重する文化が醸成されることで、チーム内の信頼関係が深まり、協力体制が強化されます。心理的安全性が高まることで、活発な意見交換や建設的な議論が促されるでしょう。
さらに、偏見にとらわれず、客観的に問題の根源を分析できるようになるため、多様な視点から解決策を導き出せるようになり、問題解決能力も高まります。
従業員の定着率が上がる
公平で働きやすい職場環境によって、従業員のエンゲージメントが高まり、離職率の低下にもつながります。
自身の個性や能力が正当に評価され、成長の機会が公平に与えられると感じることで、従業員は仕事へのモチベーションを高く保ち、企業への貢献意欲が増します。
また、ハラスメントや差別が減少し、誰もが安心して意見を言える環境で働くことで、従業員はストレスが軽減され、精神的な健康を維持できます。
さらに、企業が多様性を尊重し、公平性を追求する姿勢を示すことで、従業員のエンゲージメントが高まります。
企業ブランドイメージが向上する
アンコンシャス・バイアス研修を通じて、企業は社会的な責任を果たすとともに、対外的なイメージも高めることができます。
まず、公平性や多様性を重視する企業として認識されることで、顧客、取引先、投資家からの信頼が高まります。これは、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。
また、多様性を尊重し、公平な企業文化を持つことで、優秀な人材を引きつけることができ、採用競争力の強化にもつながります。
アンコンシャス・バイアス研修の内容
アンコンシャス・バイアス研修では、単に知識を詰め込むだけでなく、参加者自身が「気づき」を得て、行動変容を促すことが重要です。座学と実践的なワークを組み合わせることで、より深い理解と定着を促せるでしょう。
アンコンシャス・バイアスに気づくワーク
自身の無意識の偏見を認識することが、改善への第一歩となります。具体的なワークを通じて、参加者に「ハッとする」気づきを与えましょう。
具体的な方法は、次のようなものです。
自己診断テスト
質問票を用いて、自身の潜在的なバイアスを測定します。結果を客観的に見ることで、普段意識していない偏見の存在に気づかせます。
グループディスカッション
具体的なケーススタディ(例:採用面接での応募者評価、チーム内での役割分担など)を提示し、参加者同士で意見を交換させます。他者の視点に触れることで、自身の思考の偏りに気づけるでしょう。
ロールプレイング
異なる立場(例:評価者と被評価者、マネージャーと部下)になりきり、コミュニケーションのシミュレーションを行わせます。これにより、無意識の言動が相手に与える影響を体感し、自己認識を深めます。
事例分析
実際に企業で起こったアンコンシャス・バイアスによる失敗事例や成功事例を分析し、その原因と対策について議論させます。
アンコンシャス・バイアスへの対処法を学ぶ
気づきを得た上で、具体的な行動変容を促すための対処法を学ばせます。
「立ち止まって考える」習慣をつけさせる
直感的な判断や第一印象に流されず、一度、立ち止まって客観的な事実に基づいて判断する重要性を学ばせます。この時、具体的なチェックリストやフレームワークを提示しましょう。
多様な視点を取り入れるために、他人の意見を積極的に聞く
意思決定の際に、自分とは異なる意見や視点を持つ人々の意見を積極的に聞くことの重要性を学ばせます。ここには、フィードバックの求め方や、議論を活性化させるファシリテーションスキルなども含まれます。
言語化と対話のスキルアップ
自身の偏見や疑問を言語化し、オープンに議論するスキルを養わせます。ここで、相手の意見を傾聴し、建設的な対話を通じて相互理解を深める方法を学びます。
行動計画の策定
研修で学んだことを日々の業務にどう活かすか、具体的な行動計画を個人またはチームで策定させましょう。
たとえば、「週に一度、異なる部署の同僚とランチをとり、仕事の進め方について意見交換する」といった具体的な目標を設定します。
アンコンシャス・バイアス研修を行うときに注意すべきことは?
アンコンシャス・バイアス研修は、ただ実施すれば良いというものではありません。効果を最大化し、従業員の反発を招かないためには、いくつかの重要な注意点があるため、ご紹介します。
自社に適切な研修形式を選ぶ
中小企業の場合、大規模な研修を一度に行うのが難しいこともあります。自社の状況に合わせて最適な形式を選ぶことが重要です。
たとえば、次のような形式があります。
集合研修(対面)
従来のスタイルで、同じ会場に講師と受講者を集めて講義を実施するのが集合研修です。
講師との直接的なやり取りが可能で、グループワークやディスカッションを通じて深い気づきが得られやすい点がメリットです。受講者同士の一体感も生まれやすい方法です。
ただし、会場手配や参加者の時間調整が必要だったり、大人数だと個別のフォローが難しい場合があったりする点はデメリットでしょう。
オンライン研修
オンライン研修とは、講師がリアルタイムで講義をするのをオンラインで遠隔で視聴するスタイルです。
場所を選ばず参加でき、移動コストや時間も削減でき、多拠点展開の企業でも実施しやすいのがメリットです。
逆に、通信環境に左右されたり、対面より集中力が続かない場合があったりする点はデメリットです。
eラーニング
あらかじめ用意された学習コンテンツを、受講者のペースに合わせて視聴し、学べるのがeラーニングです。
従業員が自分のペースで学習でき、繰り返し学習が可能な点がメリットで、比較的、コストを抑えられる点も魅力です。
一方、受動的な学習になりがちで、深い気づきや行動変容につながりにくい可能性がある点はデメリットといえます。進捗管理が重要となる方法です。
ハイブリッド研修
オンラインと対面、eラーニングと集合研修など、複数の形式を組み合わせることで、それぞれのメリットを活かし、デメリットを補完します。
たとえば、eラーニングで基礎知識を習得後、集合研修で実践的なワークを行うといった形です。中小企業では、まずはeラーニングで基礎知識を共有し、その後、部署単位や少人数での集合研修で具体的な事例検討やワークを行うハイブリッド研修が、効果的かつ導入しやすいでしょう。
研修後のフォローアップを徹底する
研修は「一度やったら終わり」ではありません。学んだ内容を日々の業務に定着させ、行動変容を促すための継続的なフォローアップが不可欠です。
定期的な振り返りの機会を設けたり、継続的な学習機会を提供したりすると良いでしょう。また、研修中に立てた行動計画の進捗を確認し、必要に応じてサポートやアドバイスを行うのも有効です。
さらに、経営層・管理職のコミットメントも重要です。研修の重要性を経営層や管理職が理解し、率先して行動を示すことで、組織全体への浸透を促進できます。彼らが模範となることで、従業員の意識も高まるでしょう。
アンコンシャス・バイアスを学ぶならドラスタ
ここまでアンコンシャス・バイアス研修の重要性や具体的な内容について解説してきましたが、自社だけで研修を企画・実施するのは難しいと感じる人事担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、東映が提供する「ドラスタ」です。ドラスタのアンコンシャス・バイアス研修は、東映グループが長年培ってきた「物語の力」を活かし、ドラマ仕立ての映像教材とワークを組み合わせることで、受講者がまるで主人公になったかのように「自分ごと」として問題を捉え、深い気づきを得られるのが特徴です。
詳細については、ドラスタ公式サイトをご覧ください。
https://dramatic-study.toei.co.jp/
まとめ
アンコンシャス・バイアスは、誰もが持ち得る無意識の偏見であり、悪意がなくても職場における不公平やハラスメントの原因となり得ます。正しく認識し、適切に対処することで、多様な人材が活躍できる公平で心理的安全性の高い職場環境の構築、ひいては企業の生産性向上やブランドイメージ向上に直結します。
ぜひ本記事を参考に、貴社におけるアンコンシャス・バイアス研修の導入を検討し、より良い職場環境の実現に向けて一歩を踏み出してください。
なお、東映では、「アンコンシャス・バイアス」をテーマとした研修用映像作品を、複数ご用意しております。ぜひご利用ください。
ハラスメントの裏に潜む 無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス) ~職場のコミュニケーション向上のヒント~
職場の力を育む人権シリーズ 聴く力 ~相手を想う 傾聴コミュニケーション~
著者
ドラスタ編集部
(東映株式会社 コンテンツ営業部 教育映像室)
『ドラスタ』は、東映が運営する研修や学校教材の総合サイトです。
60年以上にわたり、映像制作で培ってきた物語を伝える力を活かし、
研修や教育担当者様や向けに、時代に即した楽しく学べる研修教材を提供しています。
コラム記事では、企業の方に向けて、人材育成のトレンドから用語解説について、
企業研修から防災、交通まで幅広いジャンルを専門的な視点と豊富な情報量でお届けします。





