【企業向け】SNSのリスクを減らす研修とは?リスクマネジメントを身に着けるために
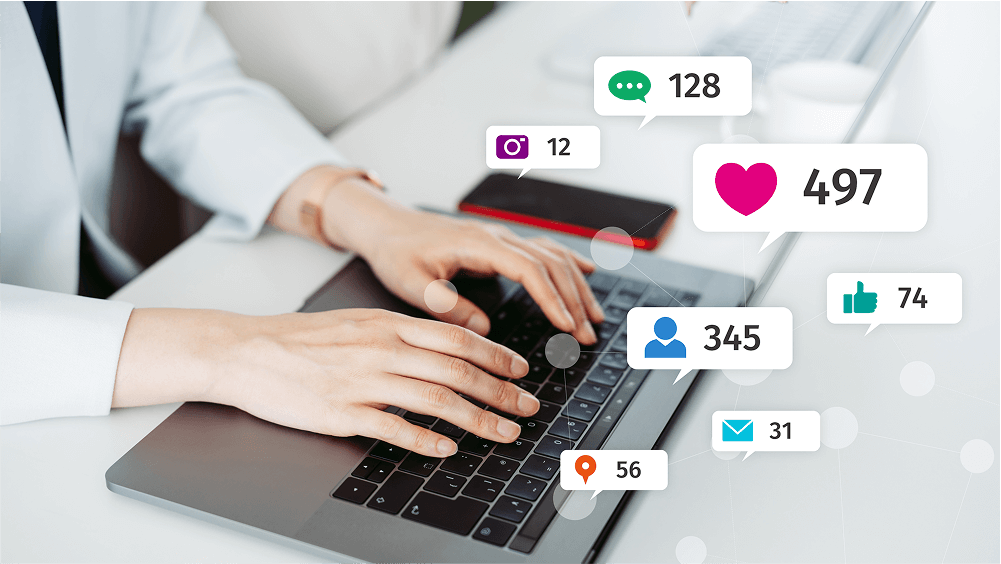
近年、SNSの普及により企業のリスク管理が複雑化しています。
従業員の何気ない投稿が企業イメージを大きく損なう可能性があり、適切なSNSリスク研修の実施は企業にとって必要不可-欠となっています。
そこで本記事では、中小企業の人事担当者向けに、効果的なSNSリスク研修の内容と実施方法について解説します。
企業のSNS炎上を防ぐために何ができる?
SNSの急速な普及は、企業にとって新たなマーケティング機会をもたらす一方で、予期せぬリスクも増大させています。
たとえば、従業員の個人的なSNS利用が、企業のブランドイメージや業績に甚大な影響を与える「炎上」に発展するケースは後を絶ちません。
中小企業においても、このリスクは決して他人事ではありません。
炎上によって企業が負うリスク
SNS炎上は、企業に多岐にわたる深刻なダメージを与えます。たとえば、次のようなリスクが挙げられます。
企業ブランドイメージの毀損
一度、失われた信頼を取り戻すには、多大な時間とコストがかかります。消費者の不買運動や企業への批判が広がり、ブランド価値が著しく低下する恐れがあります。
売上・業績の悪化
ブランドイメージの低下は、直接的に製品やサービスの売上減少につながります。新規顧客の獲得が困難になるだけでなく、既存顧客の離反も招きかねません。
採用活動への悪影響
企業の評判が悪化すると、優秀な人材の確保が困難になります。求職者が企業のSNSでの評判をチェックする時代において、炎上は採用活動に深刻な打撃を与えるでしょう。
従業員の士気低下
炎上によって従業員が精神的な負担を感じ、モチベーションの低下や離職につながることもあります。
法的・金銭的リスク
名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害、機密情報漏えいなど、内容によっては法的責任を問われ、損害賠償請求や訴訟に発展する可能性もあります。
事前準備と危機管理体制の構築
炎上を未然に防ぎ、万が一発生した場合に被害を最小限に抑えるためには、事前の準備と強固な危機管理体制が不可欠です。
具体的な施策は、以下の通りです。
SNS利用ガイドライン・ポリシーの策定
従業員がSNSを利用する際の具体的なルールやマナー、企業として期待する行動を明確に定めましょう。公私の区別、情報発信の責任、守秘義務などを明記することが重要です。
緊急時対応フローの確立
炎上発生時の報告ルート、担当部署、対応責任者、情報公開の基準、メディア対応など、迅速かつ適切な対応を行うための具体的な手順を定めましょう。
モニタリング体制の構築
自社や関連キーワードに関するSNS上の動向を定期的に監視し、不穏な兆候を早期に発見できる体制を整えましょう。
定期的な研修の実施
ガイドラインの周知徹底、炎上事例の共有、適切な情報発信の方法など、従業員への継続的な教育も重要です。
Drama-style video training東映の研修動画『ドラスタ』とは?
SNS研修が必要な理由とは?
企業がSNSリスク研修を実施することは、単にトラブルを避けるだけでなく、企業の持続的な成長と従業員の安全を守る上で極めて重要です。
企業ブランドイメージの保護
現代においては、従業員一人ひとりが企業の「顔」となり、情報発信者となり得ます。
個人のSNS投稿であっても、それが企業と紐付けられて認識されることで、企業のブランドイメージに直接的な影響を与えます。
SNS研修によって、従業員が企業の代表としての自覚を持って責任ある情報発信を促すことで、ブランドイメージの保護につながります。
法令順守と情報セキュリティ意識の重要性
SNS利用には、著作権法や個人情報保護法、景品表示法など、さまざまな法令が関わってきます。このため、従業員が意図せず他者の著作物を無断で使用したり、顧客の個人情報を漏えいさせたり、不適切な広告表現を行ったりすることで、企業は法的な責任を問われる恐れがあります。
SNS研修を通じて、これらの法令に関する知識を深め、情報セキュリティ意識を高めることは、コンプライアンス遵守の観点からも不可欠です。
SNS研修の実施方法
効果的なSNS研修を実施するためには、企業の状況や従業員の特性に合わせた方法を選択することが重要です。
研修形式の選択(集合研修、eラーニングなど)
自社や従業員の状況に合った研修形式を選択しましょう。
集合研修
同じ会場に講師と受講者を集めて講義を実施するスタイルです。講師が直接説明し、質疑応答やグループディスカッションを通じて理解を深めることができます。従業員間の意識統一や、緊急時の対応シミュレーションなど、実践的な内容に適しています。ただし、全従業員を集めるための時間調整や会場確保が必要です。
オンライン研修
講師がリアルタイムで講義をするのをオンラインで遠隔で視聴するスタイルです。場所を選ばず参加でき、移動コストや時間も削減でき、多拠点展開の企業でも実施しやすいですが、通信環境に左右されたり、対面より集中力が続かない場合があったりする欠点もあります。
eラーニング
あらかじめ用意された学習コンテンツを、受講者のペースに合わせて視聴し、学ぶスタイルです。インターネット環境があれば、時間や場所を選ばずに学習できるため、多忙な従業員や拠点が多い企業に適しています。繰り返し学習が可能で、進捗管理もしやすいのがメリットです。一方、受講者のモチベーション維持や質問対応の仕組み作りが課題となる場合があります。
ハイブリッド研修
集合研修とeラーニングなど、複数の形式を組み合わせるスタイルです。それぞれのメリットを活かし、デメリットを補完することが可能です。たとえば、eラーニングで基礎知識を習得後、集合研修で実践的なワークを行うといったかたちが考えられます。
研修頻度と対象者の設定
SNSのトレンドやリスクは常に変化するため、研修は一度きりでなく、定期的に実施することが望ましいです。
年に1回程度の全体研修に加え、新入社員向けには入社時研修に組み込む、SNSを業務で頻繁に利用する部署にはより専門的な研修を行うなど、対象者に応じた内容と頻度を設定しましょう。
外部講師や動画の活用
自社でSNSリスクに関する専門知識を持つ人材がいない場合や、より客観的で専門性の高い情報を提供したい場合は、外部の専門家(弁護士、リスクコンサルタントなど)を講師として招くことが有効です。
また、動画コンテンツは視覚的にわかりやすく、具体的な炎上事例などをリアルに伝えるのに適しています。
SNS研修に入れるべき内容
効果的なSNS研修には、以下の要素を盛り込むことが重要です。
SNS利用に関する基本ルールとマナー
まずは、個人のSNSアカウントであっても、企業名や所属を公開している場合は、その発言が企業の見解と誤解される可能性があることを理解させましょう。その上で、企業が定めたSNS利用ガイドラインの内容を具体的に説明し、遵守を徹底させることが重要です。
さらに、一度インターネット上に公開された情報は完全に削除することが困難であること、発言には責任が伴うことを認識させ、他者への攻撃的な発言、差別的な表現、ハラスメント行為が法的な問題につながることを周知します。
炎上事例から学ぶリスクと対処法
過去に発生した具体的な炎上事例(企業名を出さずに内容を説明するなど)を取り上げ、なぜ炎上したのか、企業や従業員にどのような影響があったのかを分析しましょう。
これにより、従業員は「自分ごと」としてリスクを捉え、同様の事態を避けるための教訓を得ることができます。また、万が一炎上してしまった際の初動対応(報告義務、安易な謝罪や反論を避けるなど)についても周知しましょう。
個人情報・機密情報の取り扱い
顧客情報、取引先情報、社内機密情報、未発表の製品情報など、業務上知り得た情報のSNSでの取り扱いについて指導しましょう。
写真や動画に写り込んだ情報からの漏えいリスクも説明し、細心の注意を払うよう促します。プライバシー侵害や著作権侵害のリスクについても、具体的な事例を交えて解説すると良いでしょう。
SNS研修を行う際のポイント
SNS研修を行う際の主なポイントは、次の5点です。
一方的な講義にしない
一方的な講義に始終しないように配慮しましょう。参加型ワークショップやグループディスカッションを取り入れ、従業員自身が考え、意見を交換する機会を設けることで、理解度と定着度が高まります。
最新のトレンドや事例を反映する
SNSの機能や流行は常に変化しています。研修内容は定期的に見直し、最新の炎上事例や新しいリスク要因を盛り込むことで、実践的な学びを提供できます。
従業員の理解度を確認する
研修後に簡単なテストやアンケートを実施し、内容が正しく理解されているかを確認しましょう。理解が不十分な点があれば、追加のフォローアップ研修を検討してください。
継続的な取り組みとする
SNSリスク管理は一度行えば終わりではありません。定期的な研修に加え、社内での情報共有や注意喚起を継続的に行うことで、従業員全体のSNSリテラシー向上を目指しましょう。
経営層のコミットメント
経営層がSNSリスク管理の重要性を認識し、研修実施に積極的にコミットする姿勢を示すことで、従業員の意識も高まります。
まとめ
SNSは企業にとって強力なツールである一方で、適切なリスクマネジメントがなければ、甚大な損害をもたらす可能性を秘めています。
本記事で解説した内容を参考に、貴社の状況に合わせた効果的なSNSリスク研修を企画・実施し、企業ブランドの保護と健全なビジネス運営に役立ててください。
適切な研修を通じて、従業員がSNSを安全かつ効果的に活用できるようサポートすることが、企業の未来を守る第一歩となるでしょう。
SNSリスク研修実施の際は、たとえば、東映が提供するeラーニングサービス「ドラスタ」のようなツールを活用すれば、質の高い動画コンテンツで効率的に研修を進めることが可能です。
著者
ドラスタ編集部
(東映株式会社 コンテンツ営業部 教育映像室)
『ドラスタ』は、東映が運営する研修や学校教材の総合サイトです。
60年以上にわたり、映像制作で培ってきた物語を伝える力を活かし、
研修や教育担当者様や向けに、時代に即した楽しく学べる研修教材を提供しています。
コラム記事では、企業の方に向けて、人材育成のトレンドから用語解説について、
企業研修から防災、交通まで幅広いジャンルを専門的な視点と豊富な情報量でお届けします。





